 小説
小説 『国境の南、太陽の西 村上 春樹』でカン違いについて考えた
『国境の南、太陽の西 村上 春樹』ストーリーがいつもの村上春樹でテーマがひとりっ子。すべてカン違いから来ている、というのが僕の考え。カン違いの相手を限定できればいいのだがたぶんそういう風にはできていない。カン違いをうまいこと使いこなしたい。
 小説
小説 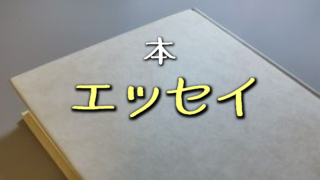 エッセイ
エッセイ  小説
小説  小説
小説  小説
小説  小説
小説  小説
小説  小説
小説  小説
小説  小説
小説