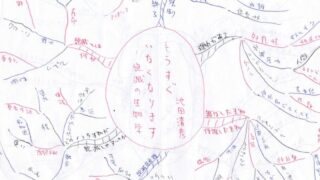 ノンフィクション
ノンフィクション 『もうすぐいなくなります:絶滅の生物学 池田 清彦』で柔軟性求む
『もうすぐいなくなります:絶滅の生物学 池田 清彦』のテーマは柔軟性。僕が今までに会った年齢に比べて若い人は、何かに打ち込んでいたり物事を面白がる能力が高かったりだった気がする。そういう人は中々絶滅しなさそう。
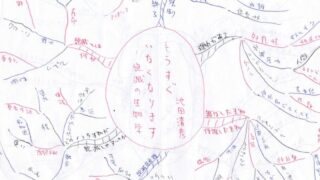 ノンフィクション
ノンフィクション  小説
小説 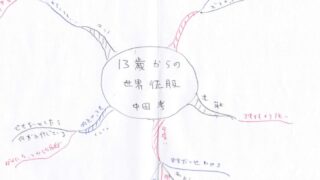 実用書
実用書  小説
小説  小説
小説 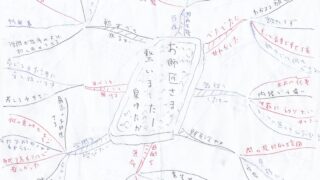 小説
小説 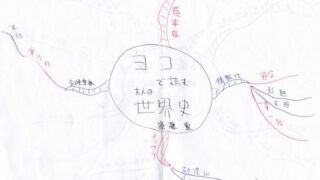 ノンフィクション
ノンフィクション  小説
小説 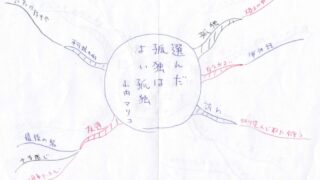 小説
小説  小説
小説