*「晴耕雨読その他いろいろ」2021/9/24投稿記事の修正転載です
「乱世をゆけ 織田の徒花、滝川一益 佐々木 功」で自分の時代小説好きを思い出した(2021/9/24)
ストーリーが司馬遼太郎風滝川一益でテーマがどちらへ進むか。第9回角川春樹小説賞受賞作。もちろん勉強のために借りてきた。時代小説だからあんまり参考にはならないけどとりあえずどんなものかと。
例のコラムで酷評されていた作品です。開始すぐに「走馬灯」が出て来て、おお、これが噂の、と嬉しくなった。でもそんなことどうでも良いのだよ。ともかく面白くて、自分が時代小説好きだったのを久しぶりに思い出せました。
そうは言ってもまずは新人賞目線で。この人にしか書けないポイントは正直思い浮かばない。どこかで見たような気がするし、何しろとり上げているのが超有名人だし。……でも面白いのだよ。
読み進めたくなるポイントは多い。僕の知ってる時代小説よりもテンポが良くホイホイ読めますよ。忍者で武将だから事件にも事欠かない。デメリットと表裏一体だけど筋書きがわかってるから続きが気になってページをめくる。
手を止めたくなるポイントもあった。誰が言ったセリフかわからなくて少し戻った箇所がチラホラ。三人称だけど神様視点気味だからだと思う。他にも時代小説好きなら気になる点があるらしいけど僕はそこまで引っかかりませんでした。
個人的に気になったのはよく出来過ぎている点。滝川一益が完璧超人過ぎて個人崇拝小説っぽくなっている。特に最後のほうでその傾向が強い。
と、色々文句を書いたがけっきょく面白いから問題ない。高校のころハマって散々読んだ司馬遼太郎を思い出した。共通点は多いと思う。まず主人公が魅力的。涼風が吹くような、とかそんな描写であらわされる、からりとした人物。女にも騒がれるが、男にはもっと騒がれる、的な。
次に忍者。わりと現実的な諜報活動からぶっ飛んだ幻術まで。これまたあるあるパターンだと思う。女性要素は少なかった?最初にちょっとあるくらいだったけどどうも時代小説と性的シーンは切り離せないような気がする。なんでだろう?
そんな感じで久しぶりに司馬遼太郎作品を思い出し楽しく読みました。あ、閑話休題はないです。あれやったら絶対新人賞取れないし。読み進めるとアラ不思議。いつの間にか頭の中に原哲夫の絵で場面が出てきます。まあ誰のせいかは明らかだけど。
方向性を示してくれるのが時代小説じゃね?
つくづく思うのだけど世の中ある程度上まで行くと運が重要。たぶんある程度までは努力でOK。でも僅差の勝負だと運不運が効いてくる。信長が死んだとき、どの場所に、どのような状態でいたか?なんてのは自分でコントロールのしようがない。どう考えても大軍引き連れて遠征中の秀吉が有利だ。
たぶんこのみみっちいバージョンが現代日本でも繰り広げられている。次の総理大臣は、とか次の社長は、とか次の部長は、とか僕ら庶民の知らないところで色々あってそこでは運不運も重要そうだ。
そうなった時にどうするか。方向性を示してくれるのが時代小説じゃね?少なくとも何かしら指針を求めて時代小説を読む、って話は聞く。戦国武将から学ぶビジネスうんたらかんたら、みたいなやつだ。
本人がどうだったかは知らないがこの小説の主人公は迷ったら自分の心の躍る方へと進んでいる。そこが最も魅力的なところだと思う。……たしかに憧れる行動だけど正直ちょっと甘い。
自分ひとり、知り合い数人ならまだしも数千人の家臣団がいて、家族含めたら万を超えるでしょ?もう打つ手なしだから最後に好きなようにやりまーす!って巻き込まれる方はたまらない。なんて酷いことを考えて、自分も大人になったのかな、と思ってます。
ビックリしたのは信玄だ。なんでこの人は後釜育てなかったの?永遠に生きるつもりだったの?若い頃には思いもよらなかった疑問がポコポコ湧いてきた。やっぱり見方って変わるものだ。
自分の時代小説好きを思い出したとても面白い本でした。
↓時代小説と化石は同じくらいロマンですなぁ。
↓歴史上の有名人物〇〇は左利きとか多そう。
↓昔の人は大変だった。それに比べて僕は砂利の運搬が限界です。
↓コンパクトかハイパワーか、現代人も方向性に悩む(どっちも買った)。
↓「晴耕雨読その他いろいろ」の読書は最初も最後も萩原浩でした。偶然ですよ。

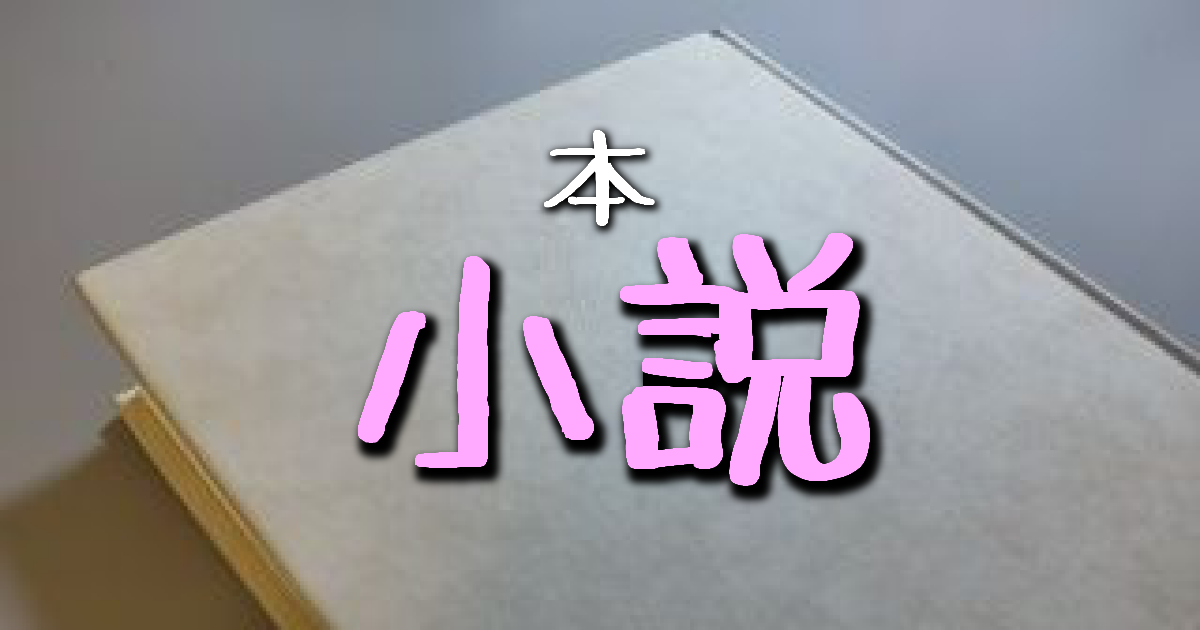







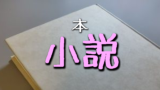


コメント